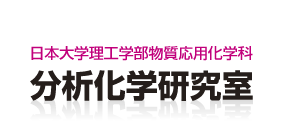「物質を測る-全元素分析で何が分かる!?」 准教授 森田 孝節
6.現在の研究について 全元素分析を達成するには元素を測定する方法が必要です。幸せなことに周期表の全元素に近い数の元素を測定する方法があります。その方法を原子スペクトル分析法といいます。この方法で測定できる元素を図4に示しました。
一口に原子スペクトル分析といってもいろいろとあるのですが,これらの方法は全て原子蒸気を生成させてから測定するということです。ちなみに原子蒸気を生成するには温度として2000~3000℃,時には1万度に近い温度で測定します。さらにこれらの方法は多元素を同時あるいは逐次に測定できます。一方,生体に含まれる第6周期までの元素を図5に示します。
この中では近年になって判明したものもあり,今後も増える可能性があります。何故なら現在測定できる濃度レベルよりも低い濃度で検出できればそれに伴い,様々な現象の解明が可能になるからです。現に生体中に金属イオンがなければ遺伝子の合成もタンパク質の代謝機能も発現しないことがわかっています。これらは微量必須元素として ppb(ng/g,10億分の1)以下のレベルで生体中に存在します。究極はこの元素の分析を通して元素1個の検出が可能になれば生命の起源を解明できるかもしれません。
また今までより低濃度の検出が可能となったことで社会に貢献した例を挙げれば水俣病や環境ホルモンなど枚挙に遑がありません。また最近では野菜の産地偽装の問題にも元素の分析が使われています。
さらに図5ではヒ素(As)が必須元素になっていますがヒ素の価数によって毒性と必須性が変化します。3価は強い毒性を示しますが,5価は必須性を示します。このように元素のみの情報だけでなく化学種の情報も必要になります。これを化学形態別分析(スペシエーション)といいます。このスペシエーションに関する研究も様々な元素について展開されています。
近年では複雑系に代表されるように1つの事象で物事を判断するだけでなく,多数の要因から結論を導く試みがなされています。事実,自然界では1種のみで多大な影響を与えるものもありますが,様々な成分が複雑に絡み合い相乗効果によって影響を及ぼすことがあります。生体中のホルモンの働きなどがこれにあたるでしょう。料理に例えれば甘みを大きく感じさせるために少量の塩をいれるのと同じです。これらを明らかにするには多元素を測定することで元素の相関関係を知ることが可能となります。そのためには幅広い濃度レベルに対応できる検出法が必要となります。また細胞1個の中の化学成分を測定しようとした場合,微少量試料(細胞一個の容積はplレベル(10-12lです。)に対応できる測定法の開発が必要です。ただし,それに特化した方法ではより多くの研究者に使われることがなくなるため,新現象の発見等が遅くなります。そこで汎用型の装置でその要望を満たす方法の開発が指向されます。
以上,様々なことについて述べてきましたが,私が現在行っている研究は
を柱とし,述べてきたことをライフワークとして研究を展開しています。
(参考図書)
元素の関する本
その他
(文 献)
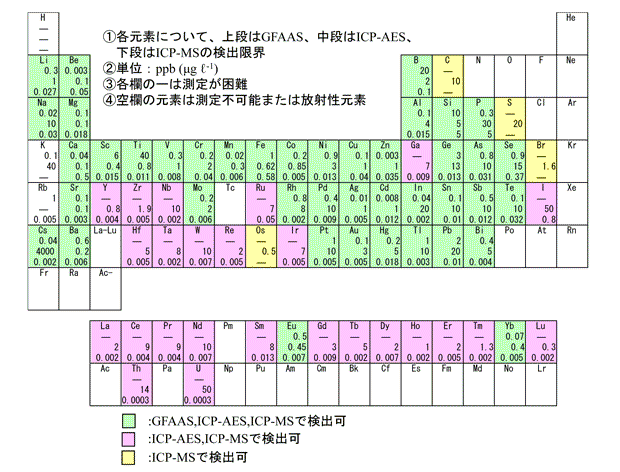 |
| 図4 原子スペクトル法で測定可能な元素と検出下限 |
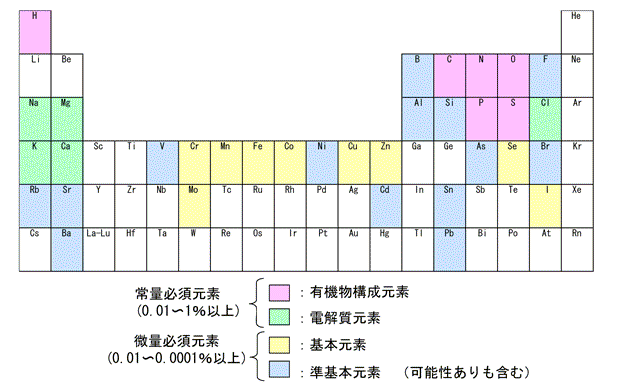 |
| 図5 生体中の必須元素(第6周期まで) |
また今までより低濃度の検出が可能となったことで社会に貢献した例を挙げれば水俣病や環境ホルモンなど枚挙に遑がありません。また最近では野菜の産地偽装の問題にも元素の分析が使われています。
さらに図5ではヒ素(As)が必須元素になっていますがヒ素の価数によって毒性と必須性が変化します。3価は強い毒性を示しますが,5価は必須性を示します。このように元素のみの情報だけでなく化学種の情報も必要になります。これを化学形態別分析(スペシエーション)といいます。このスペシエーションに関する研究も様々な元素について展開されています。
近年では複雑系に代表されるように1つの事象で物事を判断するだけでなく,多数の要因から結論を導く試みがなされています。事実,自然界では1種のみで多大な影響を与えるものもありますが,様々な成分が複雑に絡み合い相乗効果によって影響を及ぼすことがあります。生体中のホルモンの働きなどがこれにあたるでしょう。料理に例えれば甘みを大きく感じさせるために少量の塩をいれるのと同じです。これらを明らかにするには多元素を測定することで元素の相関関係を知ることが可能となります。そのためには幅広い濃度レベルに対応できる検出法が必要となります。また細胞1個の中の化学成分を測定しようとした場合,微少量試料(細胞一個の容積はplレベル(10-12lです。)に対応できる測定法の開発が必要です。ただし,それに特化した方法ではより多くの研究者に使われることがなくなるため,新現象の発見等が遅くなります。そこで汎用型の装置でその要望を満たす方法の開発が指向されます。
以上,様々なことについて述べてきましたが,私が現在行っている研究は
| (1) | 全元素分析の開発 | |
| (2) | 多元素同時スペシエーションの開発 | |
| (3) | 微少量試料導入法の開発 | |
| (4) | 固相直接導入法における原子スペクトル分析 |
(参考図書)
元素の関する本
- 玉尾皓平,桜井 弘,福山秀敏 監修:「Newton 別冊 完全図解 周期表 自然のしくみを理解する第1歩」,ニュートンプレス(2007)
- 岩澤康裕,桜井 弘 監修::「Newton 別冊 化学の“カラクリ”がよくわかる イオンと元素」,ニュートンプレス(2007)
- 桜井 弘 編,ブルーバックス B-1192 「元素111の新知識 引いて重宝,読んでおもしろい」,講談社(1997)
- 日本化学会 編:季刊 化学総説 No.27「微量金属の生体作用」,学会出版センター(1996)
- 日本化学会 編:季刊 化学総説 No.29「地球環境と計測化学」,学会出版センター(1996)
- 日本化学会 編:季刊 化学総説 No.50「内分泌かく乱物質研究の最前線」,学会出版センター(2001)
- 長尾 力 訳,シーア・コルボーン,ダイアン・ダマノスキ,ジョン・ピーターソン・マイヤーズ 著:「奪われし未来」,翔泳社」(1997)
- 今井 弘:「生体関連元素の化学」,培風館(1997)
- 桜井 弘,田中 久 編:「生物無機化学」,廣川書店(1994)
- 松本和子 監,坪村太郎,柳瀬知明,酒井 健 訳:「生物無機化学」東京化学同人(1997)
1) H. Haraguchi: Bull. Chem. Soc. Jpn., 72,1163(1999)