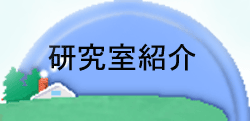
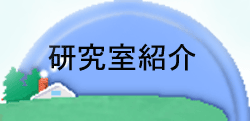
研究概要
100℃で生育する超好熱性古細菌を培養しその耐熱性のメカニズムに迫るためにD-アミノ酸を分解する酵素(タンパク質)を精製し、立体構造を明らかにすることを目指しています。また、生体を構成しているほぼすべてのタンパク質は、右手型・左手型という光学異性体の一方の型であるL-アミノ酸だけでできています。その中に微少量存在するD-アミノ酸に焦点をあて、その役割と代謝経路を研究しています。アミノ酸の生合成と分解のメカニズムやD-アミノ酸分解酵素と呼吸鎖との関係について研究しています。
卒業研究について
学習目標は、生体の命を支えている生体内の化学反応に対する知見を深めること、タンパク質の取り扱い方・機器分析法などについて基礎的テクニックを習得すること、微生物を培養し無菌操作に習熟することなどです。
大学院生をリーダーとする2〜3人のグループに属し、各グループごとに与えられた研究テーマについて研究を行います。研究成果を研修旅行を兼ねた中間発表会、日本大学理工学部学術講演会、専門の学会 (日本生化学会・日本農芸化学会・極限環境微生物学会・D-アミノ酸研究会・日本蚕糸学会)、2月下旬の卒業研究発表会などで発表します。
大学院生からの一言
院生 1我々の体を構成しているタンパク質はL-アミノ酸"のみ"から作られています。また、近年大ブームを引き起こしたアミノ酸飲料もすべてL-アミノ酸で作られています。なぜ、我々は長い進化の過程で選択的にL-アミノ酸を利用してきたのでしょう?そのなぞを解き明かすために、我々の研究室では色々な生物のD-アミノ酸を研究しています!!D-アミノ酸を研究すればするほど、生物の巧みな化学反応の機構や進化の流れなど、自分が生物でありながらも知らなかったことをいっぱーい学ぶことができ、また生命の奥深さを知ることが出来ます!!生物が好きな人も苦手な人も、我が研究室にはめったにお目にかかれない珍しい生物がいますので、ぜひぜひ来てくださーい!!
院生 2この世界にはたくさんの生物がいます。人間というひとつの生物をとっても、そこには天文学的な数の微生物が人間とともに生きているのです。 また、その生体を作っている基本成分がタンパク質で、そのタンパク質を作る原料がアミノ酸です。そして、生体内の化学反応にはタンパク質である酵素が関わっています。ここで不思議な事実があります。実験室でアミノ酸を合成すると普通はL-アミノ酸とD-アミノ酸ができるはずなのに、生体内ではほとんどがL-アミノ酸。D-アミノ酸はどこに行ったのか?そして、生体内に存在するわずかなD-アミノ酸は何のため?この不思議を追求するために私たちの研究室では、微生物を中心とした生物を利用しD-アミノ酸の研究をしています。環境微生物学研究室に来ると、いろいろな不思議に出会えるかもしれません。
実験室の紹介
|
228号室(2号館2階)
|
|
|
|
ここが長田先生のいる部屋です。 HPLCの測定装置があり、D-アミノ酸分 析グループが日々実験に励んでいます。 |
|
212号室(2号館1階)
|
|
|
ここには西村先生が居て、 ラセマーゼの研究をしています。 |
|
|
|
これは「フレンチプレス」という器械です。 硬いからをもった生物をつぶす時に使います。 溶液に高圧を掛け、一気に常圧に戻す ことにより、試料を破壊します。 |
| この部屋では酵母菌(↓)やクラミドモナス( 培養しています。 |
|
|
|
|
|
タンパク質はとてもデリケート。ちょっと暑いだけで壊れ て(変性) しま います。そこで、タンパク質を精製する
時は、低温室(4℃)にこもる ことになります。各種の 担体をつめたカラムを目的ごとに使い分けてカラムクロマトグラ
フィーを行っています。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
微生物を扱う時に大切なのは、他の種類の微生物を 混ぜない(コ ンタミネーションを防ぐ)ことです。そこで、 オートクレーブ(→)やクリーンベンチ(↓)を使います。 |
|
|
|
↑オートクレーブ(高圧の蒸気で微生物を
死滅させる)に培地を入れるところ ←クリーンベンチで植菌しているところ |
| これは連続遠心機です。
培養した超好熱性古細菌を 集めているところです。 |
 |
| これは分光光度計です。光が、吸収される度合いを測るものです。 吸光度や、吸収スペクトルを調べることができます。(→) | |
|
|
|
 |
これは超遠心機です。ローター(写真の右上)に 液体を入れ、高速で回転させることにより、地上 における重力の数十万倍という重力加速度が試 料に懸かります。「百年河清を待つ」ではありませ んが、そのまま置いておいても分かれない物を、1 時間ほどで分離することが出来るのです。 |
| この部屋では
アフリカツメガエル(↓)やカイコガ( を飼っています。 |
|
 |
|